チェンマイ大学での貢献(6):伊藤信孝 チェンマイ大学客員教授・工学部
~大学のFM 放送局からの情報発信~
チェンマイ大学工学部に客員教授として迎えられてから、早やくも7年余になりますが、ここでは本来の大学(工学部)に於ける専門講義に加え、いささか珍しい活動の一端を紹介します。タイの大学は米国の大学と類似の点が多いことも筆者のタイに対する理解の一つです。とりわけ筆者が見るタイと米国の類似点は以下のようです。
1)鉄道などの公共交通機関が少ない
2)移動の多くは自動車(長距離バスを含む)と航空機が主流
3)自動車も乗用車に次いでピック・アップトラックが普及
4)政治・経済体制は民主主義・資本主義
5)大学は前・後2学期制(米国の大学では、以前はターム制、今は学期制)
6)大学教員の昇格(昇級)は自己申請
7)大学の多くにFM 放送局がある
ここでは、上記7)に掲げたFM放送局について記す。
チェ ンマイ大学ではFM100 なるStation が学長室・副学長室が居並ぶ建物の一角にある。全学的に大学が関わり、近い将来企画・開催する、あるいは開催される各種イベントや学外の大学、企業等から の来訪者との歓談、儀式などについては、ニュース・レターの記事として写真付きで配信・配布されるが、別にFM放送を通じて地域社会に配信されるものもあ る。筆者はこの放送局を通じこれまでに3回ほど情報発信した経験がある。それらについて紹介する。時間的にはひとつの話題について10分程度である。
■3大学国際ジョイント・セミナー・シンポジウム
標 記の事業は1994年に筆者の母校である三重大学(日本)、チェンマイ大学(工学部)、江蘇大学(中国)が合意して立ち上げた学生に焦点を当てた事業であ る。大学間の国際化を推進するなかで、主として次の点に重点を置いた。大学生に対する国際教育、国際感覚の涵養、特に英語でのコミュニケーション能力の向 上、プレゼン資料作成とそれを用いたプレゼン能力の向上、協定大学とその学生間の友好・相互理解、異文化交流、グローバルな課題の共通認識と解決に向けた 提案、世界におけるアジアの役割を唱え、グローバル・テトラレンマ(地球規模の4課題)として人口・食料・エネルギ・環境を掲げた。この事業は既に立ち上 げ以来20年を超え、昨年2013年に三重大学で20周年記念事業が催された。本事業は立ち上げた3大学に限らず、参加大学数は毎年国内外の大学を含め、 平均5,6大学を数え、これまでの延べ総参加者数は優に1500名を超えている。放送では事業創設の目的・趣旨、これまでの経緯、今後の将来的展望につい てインタビュー形式で対応した。学外で初めて会う人と名刺交換して挨拶すると「ああ、FM放送で話をされていた人ですか」と言う答が放送と言う情報発信の 確かな手応えを感じさせてくれる。
■ 国際インターンシップ
筆者は、本来の専門分野としての工学部で 農業機械工学、再生可能エネルギ資源などの講義の他に、社会科学分野のビジネス・アドミニストレーション学部(FBA)でも、日本文化・日本事情としての ビジネス・エチケット、モラルについても年に1回(6時間)講義している。そこでは日本語もさることながら、国際化に向けて英語の重要性も説いている。そ うしたこともあって、これまで筆者が立ち上げた、あるいは関わった国際交流事業について聞かせて欲しいと言うことでFM放送局に招かれた。そこでは、上記 した3大学国際ジョイント・セミナー・シンポジウムに加えて、三重大学とタイの6つの大学の間で合意した国際インターンシップについてその趣旨、必要性、 プログラムの内容について説明した。現在では理系(工学)に限らず、文系にもこの事業の展開範囲が拡がり、人文・教育の学生の往来が飛躍的に増加してい る。言うまでもなく、コミュニケーション能力としての英語力の向上、異文化・相互理解、友好推進に加え、教室で学ぶ事の少ない現場でのスキル・アップが主 たる事業の趣旨である。立ち上げ当初は、受け入れ先としての企業のメリットを考えると極めて少なく、文部科学省も予算的支援も視野に入れた振興事業であっ た。なぜ企業にとってメリットが少ないかとの認識には、次のような背景がある。すなわち学生の受け入れに当たっては、単なる単純労働の機会を用意するので はなく、まさに実験、データ収集・解析、レポート作成技法、プレゼン資料作成と発表手法など、学生を中心にしたプログラムを用意し、スキル・アップを図る のが本来のインターンシップであるから、「プログラムの殆どを受け入れ企業側が用意・実施しても、将来的にその学生が自社に就職するとは限らない。受け入 れには「必ず掛かりっきりで世話をする要員を用意する必要があり、時間的にも予算的にも受け入れ側の持ち出しばかりが増えてメリットが少ない」と言うのが 本音である。唯一の利点は受け入れ学生の中に、極めて優秀な(いわゆる企業サイドの評価から見ての話であるが)人材を見いだし、採用する機会を見いだすこ とが出来るかも知れないことである。著者によるインターンシップ事業の立ち上げは、タイ現地企業訪問調査を含めると2000年ころで、発端は日系企業の多 くが海外進出を決め、赴任する企業関係者が2~3ヶ月の事前研修を受けている事を耳にしたことである。それならば在学中に国際インターンシップを経験させ ておけば、語学、スキル・アップ、相手国事情、生活体験の全てを経験させることができる。就職難をよそに、三重大学には求人が殺到し、他大学との間で差別 化を図れるのではとの期待もあった。当時の日系企業の反応は芳しくなく、中にはその趣旨に好意的に賛同を表示する企業もあったが、本社(日本)の意向を聞 いてからと言うことで、色よい返事はなかった。日本の企業でタイの大学からの学生受け入れが実現したのは2006年で、それ以後は日本人学生のタイ側への 訪問も右肩上がりで増加している。なかにはモチベーションの低い学生もいるが・・・。
ところでここ1,2年、企業側にも新たな動き が出てきている。いつまでも日本人がトップで管理運営をするのではなく、いわゆる後継者育成を図り、将来のリーダー育成に向けた動きがインターンシップ事 業を通じて出てきている事である。管理職のみ成らず開発部門での上級技術者育成も動き出している。筆者はタイの8大学(工学関係)に日系企業を同行し、戦 略の説明と人材供給の確約を依頼した。そうして採用されたタイの学生・院生達が日本での更なる教育・研修に磨きを掛けている。
■国際交流プログラム
極 めつけは筆者がこれまでに関与した国際交流事業の紹介である。グローバル・テトラレンマを課題とした国際交流プログラムとして、UNESCO/AIEJ (ユネスコ/日本国際教育協会(現在のJASSO))から2年間に亘り総額2000万円を単年度づつ支援いただいた事業がある。テーマは同じ地球規模の4 課題で、人口・食料・エネルギ・環境であるが、視点を変えて、第1年目は「アジア圏」、しかも「イスラム圏」を主対象とした内容とし、2年目は対象地域と して「アフリカ」、視点に「飢餓と貧困」を置いた。コンゴ、ケニヤ、タンザニア、モロッコなどアフリカ圏の若者に「早い時期に日本を見せる」事の意義を感 じていた。アフリカにはエジプト、モロッコ、象牙海岸の3ヶ国に国際協力事業団の短期専門家、あるいは帰国研修員のフォローアップ調査団・団長として、あ るいは国際シンポジウム招待講演者としての参加を通じて訪問経験があったので、その時の経験談を披露した。将来的にアジアの若者がアフリカの若者と手を携 えてグローバル・パートナーシップとして生きる姿を夢見ていたからである。
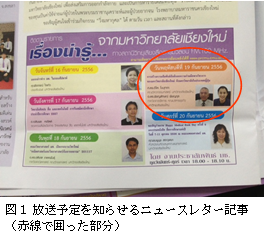

■日本の大学生
企 業の海外進出に伴い、日本国内の企業に就職しても、近い将来必ずや海外赴任を経験せざるを得ないと言うのが筆者の認識である。加えて日本の大学生にとって 国内での就職は極めて難しくなり、就職浪人が増え、政府が企業に卒後3年までは「新卒としての寛大な扱いや対応を」するよう要請したと言う話もある。こう した状況に、教員が奨学金付きで海外留学を薦めても、彼らの答の多くはNOであり、大学生の僅か20%強が“海外に出ても良い”と言っている。何故海外留 学を拒否するのか?との問いに「海外留学していては就職できない」と言う。これを聞いて筆者は耳を疑った。円滑に就職をするために海外留学をするのであっ て、国内に留まっていても就職できる保障は無い。では何故「国内に留まっていれば就職の機会が訪れるのか?」と問い直したい。不自由なく英語でのコミュニ ケーションができるわけでもなく、人並み外れたスキルや海外経験があるわけでもない、積極的に海外に出て、自らに投資をする積極性もモチベーションもない 人間を採用側が対象にする筈はない。何と言う心狭い世界での発想であろうか。卒後3年までは「新卒扱いで」の要請も開いた口がふさがらない。職を求める側 が、何の努力もせず、ひたすら就職の機会を待ち続けるだけで自動的に、いつかはその機会が訪れると考えさせるような対応が正しいはずがない。途中採用の機 会も無いわけではない。本人自ら努力し、熱い思い (Enthusiasm) を見せられない者に採用する側が微笑むことはない。大学教育も事なかれ主義が先行し、ひ弱になったものである。大学の国際交流も、あまりにも性急なアウト プットを求めるが故に、アウトカムの少なさ、レベルの低さ、礼を尽くすことを忘れた対応の無責任さに言葉を失う。
■タイの大学生
筆 者が担当する講義は大学院修士課程の学生が対象である(上記国際インターンシップの章参照)。日本の大学生と比較してタイの学生はどうですか、と言う質問 をよく受ける。定年退職後であるため過去を振り返ってその記憶を遡るが「そんなものだったかな」と言う記憶しかない。講義は英語と言うこともあり、履修受 講生は1クラスで10名から20名程度。最終評価はレポート、出席率、中間試験、期末試験を総合して行う。評価には英語の理解度が重要な要素となる。すな わち講義内容を理解していても英語で解答できないのか、英語は出来るが内容を理解していないのかの判定が難しい。そのためレポートは1回に尽き20~30 頁の量を総数5~6回提出させる。提出法は全て電子メールでの送付を義務づける。分量、期限厳守でない場合は受け付けない。講義資料も筆者自前の手作り資 料を講義修了と同時に惜しげもなく学生に提供する。同じ資料を利用せず、改善・新情報を挿入して改訂するためである。またハードコピーによる用紙と時間の 節約が大きい。レポートのメールでの提出は癖のある手書きの解読を防ぎ提出と提出日及び量の確認、期限厳守に主たるねらいがある。メールでのレポート提出 は上記のような利点がある一方で、他人のモノをコピーもできる。この問題への完全な対応は難しいが、期末試験の多くをレポートの問題を選択させることで対 応している。期末試験は英語での解答なれど手書きでの解答だからである。
問題は講義開始時間に多くの学生が遅れてくる。そうした学生に限 り、後ろの方に座り、隣の学生と私語で話をする。このような学生には近くに行って注意し退出を命じる。聞かない場合は執拗に注意を繰り返す。こうした努力 もあって後期が始まって5,6回の講義が過ぎた頃、学生の5,6名が筆者より早く教室に来て、黒板掃除、プロジェクタのスイッチON、部屋のカーテンの開 閉を済ませ待機するようになった。正直嬉しかった、自分の言うことが理解されたと感じた瞬間であった。この話を聞いた同僚の教員は「ええっ、そんな事 が!」と言わんばかりの表情で沈黙した。学生達とはその後も付き合いがあり、クラスでのパーテイ開催が彼らの側から企画されている。 誠に嬉しい限りである。





